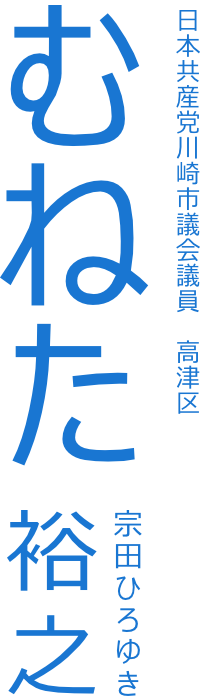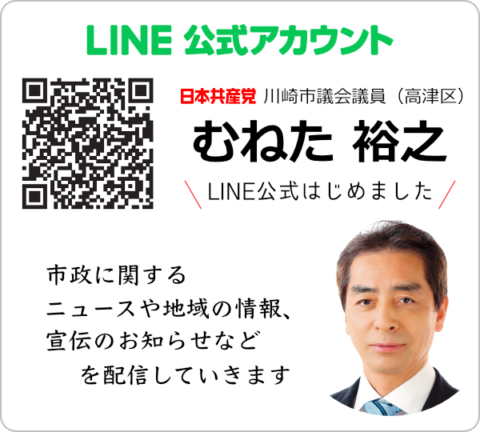臨海部の水素戦略:オーストラリアからの輸入水素は取りやめに
25年2月28日、川崎市議会3月議会で、日本共産党川崎市議団を代表して宗田団長が代表質問を行い、「臨海部の水素戦略ついて」質疑しましたので、紹介します。
●質問
臨海部の水素戦略についてです。
臨海部の水素戦略関連予算は、液化水素サプライチェーンの商用化実証事業に向けて、扇島地区への一般道路・高速道路アクセスに5億円、岸壁・港湾道路等港湾施設の基盤整備に1.9億円など計6.9億円が計上されています。事業者の当初の計画ではオーストラリアで褐炭から水素を作り、液化水素にして船で運び、扇島のJFE跡地の水素拠点で受け入れるとして、28年度から30年度に実証事業を実施、30年度から商用化するとされていました。川崎市政だよりでも3ページも使い「海外から大量の水素を運ぶ」と報じています。
しかし、28年度からの商用化実証について、政府の「産業構造審議会グリーンイノベーション部会」は昨年9月、「豪州ビクトリア州からの水素調達は難しくなった」として国内からの水素調達に切替えることを発表しました。これは重大な計画変更です。国は、昨年9月に商用化実証におけるオーストラリアからの調達を中止したのに、なぜ、委員会などで報告しなかったのか、伺います。また、オーストラリアからの水素調達は何が原因で中止したのか、伺います。国内水素に切り替えるということですが、どこから調達するのか、グレー水素も含むのか、伺います。
◎答弁
グリーンイノベーション基金事業を活用した、民間事業者による「液化水素サプライチェーンの商用化実証」の計画変更につきましては、令和6年9月に開催された、経済産業省のワーキンググノレープにおいて、技術実証に活用する水素源を、海外調達から国内調達に変更するととなどが、民間事業者からの説明を踏まえ討議されております。その際の民間事業者の資料につきましては、国のホームページに掲載されておりますが、民間事業者からの報道発表は行われていないところでございます。今後、社会実装に向けた民間事業者の事業進捗を踏まえ、本市の水素戦略に関わる取組の進展に応じて、議会への情報提供を行ってまいりたいと存じます。
次に、商用化実証段階において、水素の調達先を国内に変更した理由につきましては、豪州における許認可取得と設備建設に必要な時間を考慮すると、 2030年度までに実証を完了することが困難であるとともに、液水素サプライチェーン構築に向けた国際競争が激化している中で、競争力の獲得に向けて、 2030年度内に実証を確実に実施するためと、関係事業者から伺っております。
次に、商用化実証段階における国内水素の調達先や製造方法等につきましては、関係事業者において、現在、検討・調整中であると伺っております。なお、 2030年度以降の社会実装・商用段階におきましては、水素社会推進法に基づく計画認定制度を活用し、海外から調達ナる低炭素水素を、扇島地区で受け入れて、周辺地区に供給する計画に変更はないと伺っております。
●再質問
臨海部の水素戦略についてです。 【臨海部国際戦略本部長】
答弁で、昨年9月、オーストラリアからの輸入水素は商用化実証には間に合わないとして国内水素の調達に切り替える国の計画変更があったことを市は認めました。しかも、これだけの重大な計画変更を今まで関連する委員会に報告がなかったことは、重大です。
国内水素の調達についてです。
国内の調達先について「現在、検討・調整中」という答弁で、まだ決まっていないということです。化石燃料から作る「グレー水素も含むのか」という質問に対して、否定しませんでしたから、含むこともあるということです。
これら水素のほとんどは市内の天然ガス発電所で混ぜて使うことになります。そうなると国内で再エネや化石燃料から水素を作り液化して船で川崎に運び、また、発電所で混ぜて使うということです。わざわざ水素に変換し液化して運ぶよりも、その電力をそのまま送電すればよいのではないですか、伺います。化石燃料から作るのであれば、CO2を大量に出して水素を作り、また、発電してCO2を出すことになるのです。なんて無駄でCO2を大量に排出する計画になると思わないのか、伺います。
海外水素の調達についてです。
「30年以降は、海外から水素を調達する」という答弁でしたが、まだ、どこから調達するのか決まっていません。これに関して、水素を調達・運搬・貯蔵する会社、日本水素エネルギーに資本参加すると発表していたINPEXが出資を見送ると昨年末に報道されました。新聞報道では「水素の国内需要が停滞し、運搬コストも大きいことから投資効果が得られないと判断した」と報じています。調達先も出資先も決まらないということでは、海外からの水素輸入事業は、全く目途が立たないのではないですか、伺います。
◎答弁
グリーンイノベーション基金事業「液化水素サプライチェーンの商用化実証」における国内調達の水素につきましては、技術実証を目的として、液化水素の受入れ・出荷設備や貯蔵タンクなど、商用規模での機器の性能確認や、液化水素基地の全体運用、液化水素運搬船による外洋航行時の運用等に活用するもので、ガス火力発電所等で使用することは予定しておりません。
また、社会実装・商用化段階におきましては、水素社会推進法に基づく計画認定制度を活用し、海外から調達する低炭素水素を、扇島の周辺地区に供給する計画と伺つております。
次に、海外からの水素の調達につきましては、国際的な政治情勢や世界的なインフレ等の諸課題があるものの、関係事業者から、商用化実証を着実に進めるとともに、複数の候補地などを含め、国内外の関係機関等と協議調整を行っており、 2030年度からの社会実装・商用化の実現を目指していると伺っております。
●再々質問
臨海部の水素戦略についてです。
28~30年度の国内水素の調達について、「火力発電所には使用しない」という答弁ですが、それでも化石燃料や再エネから水素に変換し、液化水素にして船で運ぶことには変わりなく、それぞれの段階で膨大なエネルギーを使い、CO2を大量に排出することには変わりません。
30年度以降の海外水素の調達については、「国内外の関係機関等と協議調整を行っている」という答弁で、まだ、決まっていないということです。
技術的な課題についてです。
CCS技術について、米国の会計検査院は、政府が補助金を出した火力発電CCSは8件中7件が失敗と発表し、米国ではコスト面からCCS事業は困難と判断したようです。CCSの許認可について、オーストラリアでも許認可が取れるかどうかのリスクもあり、なによりCCS工場ができるかどうかの保障もありません。他国にとっては、日本の水素のために排出したCO2をなぜ、自分の国の地中に埋めるのか?と考えるのは当然です。このようにCCSの商用化は、技術面、コスト、許認可の取得を考えるときわめて困難だと考えられます。
水素を「つくる」「ためる」「はこぶ」の水素サプライチェーン構築についてですが、この実証事業は世界初であり、個々の事業である水素製造、水素運搬船からの荷役、揺れる船からの極低温の液化水素を貯蔵・管理する技術、また、陸揚げする技術などはすべて世界で初めての技術です。どの技術・事業も実証までは行きついておらず、事業が成り立つかどうかの調査段階で商用化まではとてつもなく遠い事業です。これだけの課題があるのに、扇島の水素拠点のために道路や岸壁を整備する必要があるのか、市長に伺います。
◎答弁
首都圏へのエネルギー供給拠点であ,る川崎臨海部が、カーボンニュートラル社会においても、持続的に発展していくためには、水素を軸とした力ーボンニュートラルなエネルギーの供給拠点へと変革していく必要があると吉えております。
こうした中、関係事業者が、技術的課題を含めた諸課題に対応しながら、液化水素サプライチェーンの社会実装・商用化の実現に向けて取り組んでいるところでございます。
本市といたしましては、関係事業者と一層緊密に連携し、国の支援制度を活用した水素の受入・供給拠点の形成や、水素サプライチェーンの構築を着実に進めてまいります。
●最終意見
臨海部の水素戦略についてです。
政府から「オーストラリアからの水素調達は困難」と判断され、その他の地域、国内、海外からの水素調達も目途が立っていないことが明らかになりました。さらに、発電コストも火力発電の2倍にもなり、CCSなど技術的課題も多数あり、多くの国では実証化・商用化まで相当かかること、各国の許認可が取れるかわからないことなど、まさに事業として成り立つ目途も立っていないことが明らかになりました。
世界的には、水素の混焼発電は、40年代以降もCO2を大量に出し続け、化石燃料による発電の延命措置だと多くの批判を浴びています。
わが党が提案しているように、臨海部のJFE跡地利用は水素戦略ではなく、ペロブスカイトなど太陽光中心の再エネ・省エネ企業を誘致し、生産・供給拠点にすれば、日本初の大都市での再エネ自給自足のモデル都市にすることができます。