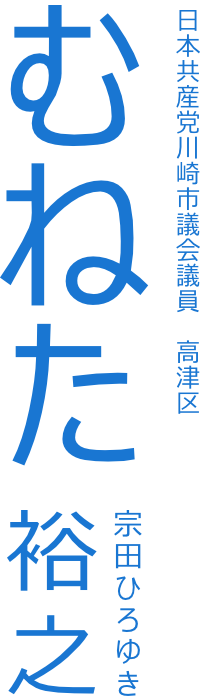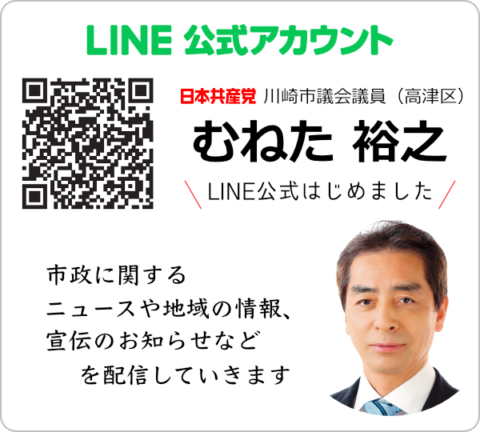臨海部に太陽光発電(ペロブスカイト)の開発・生産拠点を

液化水素の輸入は30年以降、水素発電の見直しを
むねた議員は、決算審査特別委員会で「臨海部の脱炭素戦略」について質疑を行いました。最初に、JFE跡地(扇島)において、オーストラリアで液体水素を製造し、輸入・貯蔵する拠点を作る水素サプライチェーンについて質問、答弁は、液化水素を輸入は、これらから実証実験ということで、オーストラリアでの認可、日本の認可も取って、商用運転の開始は、30年度以降までずれ込むということでした。むねた議員は、「先進国は、35年までに電力部門のCO2排出ゼロを目指すということですから、臨海部の水素発電は、全く間に合いません。CO2を出し続ける火力発電を延命させるだけ」と水素発電の見直しを要望しました。
ペロブスカイト太陽電池で人口構造物全体を発電設備に
また、むねた議員は、最近注目されている太陽光発電(ペロブスカイト太陽電池)について、政府は5月の「GX実行会議」で2兆円の基金の投入先として「次世代太陽電池(ペロブスカイト)について開発を進め、25年から市場投入する」としていること。また、その特性と可能性について「厚さがおよそ1ミリメートルと非常に薄く、軽くて折り曲げることができ、設置が難しかったビルの壁や窓にも設置でき、各社が製品化もしている」、「これを使えば、建物、道路、駐車場、倉庫など人口の構造物全体を発電設備にすることができ、都市部でも臨海部全体でも大きな電力を作ることができる」ことを紹介。
太陽光発電の需要は爆発的に増大、臨海部に生産拠点を
むねた議員は川崎市も、地域エネルギー会社の設立や初期費用がかからないPPAによる太陽光パネルの設置、ゼロエネルギーハウス(ZEH)なども対象とした太陽光設備補助金などを始め、太陽光発電の需要は爆発的に増大するとして、臨海部にペロブスカイトの企業を誘致して開発・生産拠点を作ることを要望しました。