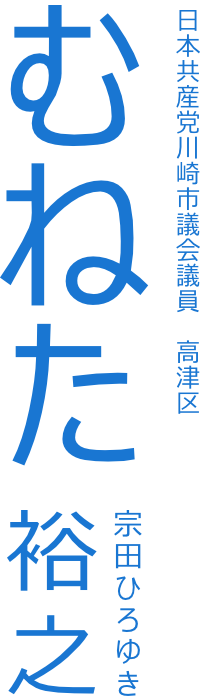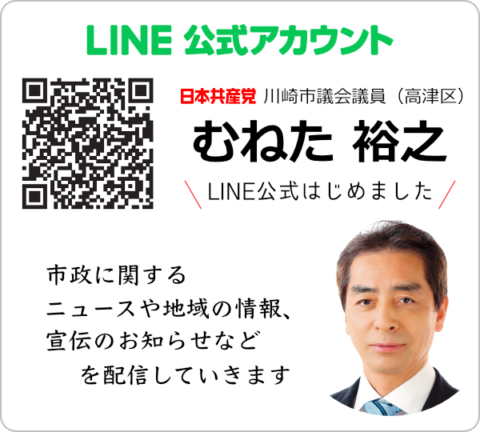臨海部をペロブスカイト太陽電池の開発・生産拠点に
9月25日、決算審査特別委員会でのむねた議員の質疑を紹介します。
・2款4項1目、臨海部国際戦略費の脱炭素戦略について、伺います。
水素サプライチェーンについて
- オーストラリアの水素サプライチェーンについての認可が取れるのは、いつごろか?
液化水素サプライチェーンの構築に向けて、現在、関係企業が、オーストラリアの関係機関と、調整を行っているところと伺っております。
●宗田
・現地、オーストラリアのビクトリア州では、相当苦労しており、認可を取るのに遅れるとの見方もあるということです。
- オーストラリアから液化水素を輸入するのは、いつごろからか?
●答弁
水素社会推進法に基づく計画認定制度の活用を見据え、2030年度を目途とした国際水素サプライチェーンの構築を目指し、プロジェクトの具体化に向けて関係企業と検討しているところでございます。
●宗田
・これらから実証実験ということで、オーストラリアでの認可、日本の認可も取って、商用運転の開始は、30年度以降までずれ込むということです。
- 市内の天然ガス発電所に水素を混ぜて混焼するのは、いつごろからか?その混焼率は?
●答弁
水素社会推進法に基づく計画認定制度の活用を見据え、2030年度を目途に水素利用が可能となるよう、プロジェクトの具体化に向けて関係企業と検討してぃるととろでございます。
こうした中、株式会社レゾナックにおきましては、川崎事業所において火力発電設備りプレース計画の環境影響評価手続きに着手しており、その「計画段階環境配慮書」では、運転開始は2030年度内を予定し、運転開始時の水素混焼率は、容積ベースで30%として計画していると伺っております。
・
●宗田
- 市内の火力発電所を水素の専焼発電に切り替えるのは、いつごろからか?
●答弁
市内の各発電所における水素専焼発電への移行時期につきましては、それぞれの運営事業者が諸条件を踏まえ判断されるものと考えております。
現在、エネルギー基本計画の改定に向けた議論の中で、国全体の電源構成について検討が行われることが見込まれておりますので、こうした動向を踏まえながら、関係企業と連携して水素サプライチェーン構築に係る取組を推進してまいります。
●宗田
・JERAのロードマップでも、40年代まで混焼を続けて、専焼は50年以降となっていますので、2050年までは、発電所からCO2を出し続けるということです。
- 国際エネルギー機関(IEA)のセクター別ロードマップでは、先進国において「電力熱部門」でのCO2排出ネットゼロにするのは、いつとしているのか?
●答弁
2023年10月に公表されました、 1EAのエネルギーに関する年次報告書である「World Energ y Outlook 2023」には、 2035年までに先進国における電力部門でのC02排出をネットゼロとするシナリオが記載されております。
●宗田
・JERAの計画では、2050年まで発電所からCO2を出し続けますが、先進国は、35年までにCO2排出ゼロを目指すということですから、日本の水素発電による電力は、全く間に合いません。CO2を出し続ける火力発電を延命させるだけです。
(要望)
・水素発電の見直しを要望します。
●宗田
ペロブスカイト太陽電池について
・欧米やほとんどの先進国は、35年までに電力部門の再エネ比率は100%で、その中心は太陽光と風力です。その中で近年注目されてきたのが、ペロブスカイト太陽電池です。
- 政府は5月の「GX実行会議」において、「次世代太陽電池(ペロブスカイト)について」どのような方針を打ち出したのか?
国が本年5月に実施したGX実行会議においては、グリーントランスフォーメーションの加速に向け、脱炭素の産業・社会構造への転換に関し、 2040年を見据えた「GX2040 ビジョン」をとりまとめるとととし、論点の1つとして提示された産業構造のうち、ペロブスカイト太陽電池については、大型プロジェクトとして集中支援を行っていくことが議論の方向性として示されました。
これを踏まえて、 8月に実施したGX実行会議においては、ペロブスカイト太陽電池を国内外の市場創造・需要獲得に向けた新たな産業のーつとし、令和7年度GX関連概算要求案として、国内サプライチェーン構築に向けた支援を行うことが示されております。
●宗田
・政府も5月の「GX実行会議」で2兆円の基金の投入先として「次世代太陽電池(ペロブスカイト)について開発を進め、25年から市場投入する」としています。
- ペロブスカイト太陽電池の特性と用途について伺います。
●答弁
ペロブスカイト太陽電池は、光を吸収する材料をフィルムなどに塗布・印刷して製造することが可能で、軽量・柔軟という特性を有していることから、低耐荷重性の屋根や壁面等のこれまで設置が困難であった場所への設置が可能になると言われております。
また、主な原材料であるヨウ素は、日本が世界第2位の産出をしており、サプライチェーンを他国に頼らず安定して確保でき、エネルギーの安定供給にも資することが期待されております。
●宗田
・ペロブスカイトは、横浜の大学で開発されたもので、厚さがおよそ1ミリメートルと非常に薄く、軽くて折り曲げることができ、広く普及する既存のシリコン製の太陽電池では設置が難しかったビルの壁や窓、湾曲した屋根にも置けるもので、各社が製品化もしています。
・これを使えば、建物、道路、駐車場、倉庫など人口の構造物全体を発電設備にすることができ、建物自体で消費する電力を賄うことも可能であり、都市部でも臨海部全体でも大きな電力を作ることができます。
- 各企業において、どのような製品が開発されているのか?
●答弁
国の示す資料によりますと、ペロブスカイト太陽電池の種類としては、光を吸収する材料をフィルムに塗布印刷した「フィルム型」や、既存の建材ガラスにぺロブスカイトを活用し、一体化させた「ガラス型」、シリコ太陽電池とぺロブスカイト太陽電池を組み合わせ、高い発電効率が期待できる「タンデム型」の太陽電池の開発が進められており、特にフィルム型では、製品化に重要となる大型化や耐久性の面で、日本が世界をりードしていると言われております。
●宗田
・現在、各会社ではこぞって開発が進められており「ビルの窓や外壁を発電所に」「発電するガラス」などゼロエネルギーハウス(ZEH)と合わせて販売も開始されています。経産省は官民協議会を設置し、170を超える企業が参加しています。神奈川県はペロブスカイト太陽電池の実用化に向けた実証や普及啓発のために23年12月に、(株)日揮などと連携協定を締結しています。
- 川崎市の太陽光発電の推進にとって、市内での需要はかなりあるのではないか、伺います。
●答弁
「ペロブスカイト太陽電池」につきましては、従来の太陽発電設備と比較し、その特性から様々な箇所に設置が期待でき、これまで以上に再生可能エネルギーの普及拡大に寄与するものと考えられ、社会実装がなされれば、市内での需要も大きいものと考えております。
●宗田
(要望)
・川崎市も、地域エネルギー会社の設立や初期費用がかからないPPAによる公共施設への太陽光パネルの設置、ゼロエネルギーハウス(ZEH)なども対象とした太陽光設備補助金などを始めました。太陽光発電の需要は爆発的に増大します。臨海部にペロブスカイトの企業を誘致して開発・生産拠点を作ることを要望します。