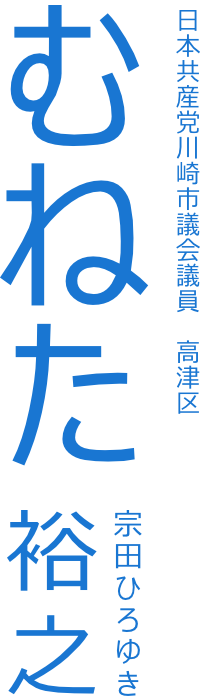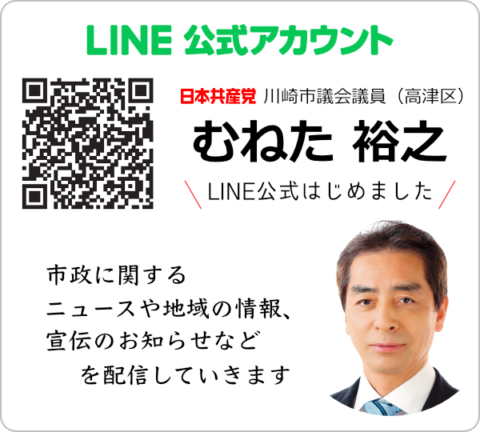震災ボランティア・南相馬の参加者感想−「小高を生で見て衝 撃!」「これをスタートに来月も」
川崎中部地区としては、初めての南相馬へのボランティアでした。
1日目は、南相馬市の渡辺市会議員から現地の実態や状況を聞きました。
2日目は、全国青年ボランティアの人たちと仮設住宅に訪問して、
お米やカボチャなどの物資を届けながら、聞き取り活動をしました。
2日目の夕方には、20キロ圏内の小高地区を見て回り説明を受けました。
3日目は、別の仮設住宅に訪問して、物資を届け、聞き取り調査をしてきました。
「他県と違い、復旧も進まず、家族もバラバラで希望が持てない状況」
今まで宮城県石巻には、15回にわたり震災ボランティアの活動をしてきましたが、
福島県は、他県とは違う実態がありました。
一つは、家族一緒に暮らすという希望が持てない状況があります。
仮設住宅に若い人、子どもが少ないのです。
放射能の影響で少なくない若い人たちが県外などに避難していて、戻って来れず、
老夫婦だけが残り、家族バラバラに暮らしている世帯がおおくありました。
元の家に戻りたいといってもいつ戻れるかわからず、
戻っても若い家族が戻って一緒に暮らせる保証もありません。
二つには、放射能の影響で、ガレキ撤去、除染が進まず復旧さえも、
まだまだこれからと言う状況です。
放射能汚染されたガレキなどの中間、最終処分場が決まらず、
小高地区は壊れた家屋、車は放置されたままの状態で、
去年の石巻の4月以前のような状態です。
他県に比べてはるかに復旧も復興も進んでおらず、被災者は将来展望を持てない状況でした。
この事実を多くの国民に知らせるとともに、国や行政の支援、ボランティア活動も、
もっともっと必要です。
今回、初めて参加した方の感想を紹介します。
「これをスタートに来月も来たい」O君(30代、男性)
まわりに被災にあった人もいて他人事ではないと思っていた。
職場でも多くの人が行きたいと思っていたが休みが合わずにいた。
被災者の生の声を聞きたいと思ってきたが、いろんな声が聞けた。
多くの被災者が「早く家に戻りたい」と思っていた。
小高地区を生で見て衝撃を受けた。
この声や実態を届けていきたい。
これをスタートに来月も来たい。
「もっとこの実態を報道して欲しい」T君(20代、男性)
今回来て見て認識が変わった。
被災された方は、難民のように710個所も避難場所を渡り歩いて
やっと仮設にたどり着いた。
そしていつか故郷に戻るというのが生きて行くうえで支えになっていた。
そういうことを聞き取りながら、ボランティアが人の役に立っていると実感した。
人がもっと必要、もっとこの実態を報道して欲しい。
「小高地区を見て凄い衝撃」I君(30代、男性)
訪問したら「ジュースを飲んでって」と言われた。
「来てくれて嬉しかったんだな」と実感した。
小高地区を見て、すごい衝撃、凄いところを見た。
本当にあんなところが現実にあるんだと思った。
これから事実を広げていきたい。
「全国から若い人たちが集まって来ていて凄い」Kさん(40代、女性)
全国から若い人がこんなに集まって来ていて凄い!と感じた。
仮設住宅を訪問して、「要望したら郵便ポストがついた」と喜んでいた。
小さなことでも実現していく、地道な活動が大切。
これだけに終わらせたくない。
全国の人たちと手をつないでまわりの人に伝えていきたい。