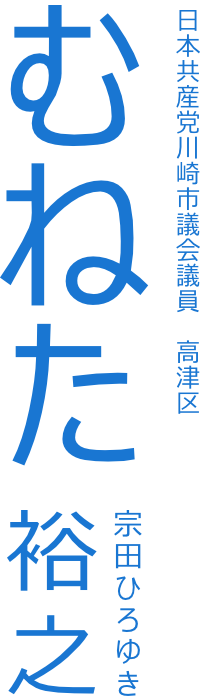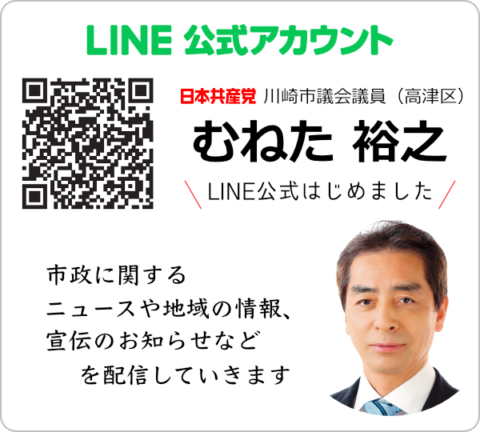最低賃金の引上げを求める意見書ー総務委員会での質疑
陳情第67号「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」について、1月19日に行った総務委員会での私の質疑(大要)部分を紹介します。
(*番号(下線)が質問事項で答弁(太字)は経済労働局)
(川崎市の雇用・労働実態について)
① 総務省の「就業構造基本調査」で、川崎市の1997年と2012年を比較して、非正規労働者数の変化は?
答弁・・「非正規労働者は14万人から23万人へと1.7倍に」
② 同じ調査での、年収300万円未満の労働者の比率、年収200万円未満の比率は?また、20代の年収300万円未満、年収200万円未満の比率は?
答弁・・「年収300万円未満の割合は43.8%、20代では59.5%。年収200万円未満は26.4%、20代では30.5%」
・年収300万円未満の割合は44%、20代では60%/年収200万円未満は4人に一人、20代では3人に一人がワーキングプアという実態。
・川崎市でも非正規労働者が急激に増え、低賃金で不安定な仕事についている人、働いてもまともに暮らせない人、特に若者のワーキングプアが増えている
(若者の生活実態について)
③ 総務省の「家計調査」で、34歳以下単身の方の実収入について、2002年と2015年の額は?
答弁・・「2002年が30万8830円、2015年は30万3460円」
・この13年間で、若い世代の実収入は、6370円減っている。
④ 34歳以下単身の方が神奈川の最低賃金930円で法定労働時間の上限で働いた場合の収入と年金保険料、健康保険料、市県民税は?
答弁・・「収入は16万1634円、公的年金保険料22053円、健康保険料10979円、個人住民税9670円」
・法定労働時間の上限173.8時間働いても、月額16万1634円、年額では194万円。年収200万円にも届かず、いわゆるワーキングプア状態/16万円から年金・健康保険料、税金を引くと11万9000円。そこから水道光熱費(生活保護費の単身者支給額)40800円を引くと78000円/ここから家賃約7万円を引くと残り8000円/この額では食費・衣服費はとても賄えない/要するに最低賃金でフルタイムで8時間働いても普通の生活ができない
・厚生労働省・社会保障審議会の試算では月の最低生活費は19万2000円、時給にすると1500円以上必要だという結果が出ている。
(ひとり親世帯について)
⑤ 一人親世帯の貧困率とOECD内の順位は?
答弁‥「貧困率は54.6%、OECD内では33位で最下位」
・日本の一人親世帯の半分が貧困状態で、先進国では、最も貧困な状態にある
⑥ 日本の母子世帯の就業率は?
答弁・・「就業率は80.6%」
・就業率80.6%、これはOECDで最も高いレベル/母子世帯では、8割の世帯が働いているのに貧困から抜け出せない/日本の賃金がいかに低いかがわかる
・要するに、日本の一人親世帯は、先進国で最もひどい貧困状態にあり、賃金が低いために働いても貧困から抜け出せない状態
(お年寄りの生活実態について)
⑦ 高齢者の就業率は?
答弁・・「高齢者の就業率は20.8%」
・国際比較では、ドイツ5.4%、アメリカ17.7%、日本は20.8%で明らかに「働きすぎ」と言われている/しかも、内閣府の調査では、就労を希望する最大の理由は「収入が欲しいから」49%/年金だけでは生活していけないのが理由。
⑧ 総務省の「家計調査」で、高齢夫婦世帯(世帯主無職)の実支出と実収入で2000年と2015年のそれぞれの額は?
答弁・・「2000年の実支出256487円、実収入246522円。2015年の実支出278195円、実収入211135円」
・2000年、2015年どちらも収入より支出のほうが多い、大幅な赤字/2000年の赤字額、約1万円が2015年67000円になり、15年で赤字額は6.7倍に/仮に1000万円の貯金があっても12年程度でなくなり貧困に陥る可能性がある。
・年金のベースは現役の時の賃金ですが、今、賃金が下がり続けている=年金は今よりさらに下がる可能性大/要するに今でも年金者は年金収入だけでやっていけないのに、賃金が下がればさらに生活ができなくなる
・以上のように、若い世代、ひとり親世帯、高齢者世帯、どの階層も賃金が低いために働いても生活が成り立たない人が増えている
(市内の中小企業にとって)
・川崎市には、市内中小企業の受注機会の増大と従業員の労働環境の改善などを目的とした川崎市契約条例がありますが、
⑨ 川崎市契約条例の特定業務委託契約の作業報酬下限額は、何を基準に?
答弁・・「平成27年10月に契約条例を改正し、基準を生活保護基準から最低基準に改めた」
・最低賃金を上げることは市の公共工事の単価を上げることになるということ。
・昨年、建設業協会の方と懇談/100万円未満の少額の仕事などは、「価格が低すぎてやっても元が取れない」や「人手不足だが、高い賃金を払えないために若い人が来ない」という悩み
・要するに、最低賃金の引き上げは、市内の中小企業への発注単価、従業員の賃金引上げ、後継者つくりのためにも必要
(国際的にみて日本の最低賃金はどうなのか)
・日本の最低賃金(平均)は、昨年引き上げられ798円から823円に
⑩ 賃金の中央値に対する日本の最賃の比率は?OECDの平均値は?OECD内の順位は?
答弁・・「日本は39.8%、OECDの平均値は50%。日本はOECD内では、26か国中22番目で下から5番目」
・OECDでは下から5番目/OECD平均は50%(約1000円)/せめてOECD平均にすべき
・昨年、国際通貨基金(IMF)は対日審査報告書で、日本政府に賃金と最低賃金の引き上げを勧告した。
・意見書にあるように、政府と経団連も含めた合意目標は2020年までに平均1000円/しかし、安倍政権の「年率3%程度」という目標では平均1000円に到達するには7年もかかる/最賃は早急に引き上げないと政府の目標も達成できない
・最賃を引き上げるべきという声は自治体の首長からも/静岡県の湖西市長は、アメリカが最賃を15ドル(約1800円)に引き上げようとしていることを指摘し「大幅な引き上げを」国に要望。
・以上のような点から、市民、中小企業、地方自治体にとっても最低賃金の引き上げは必要だと考える